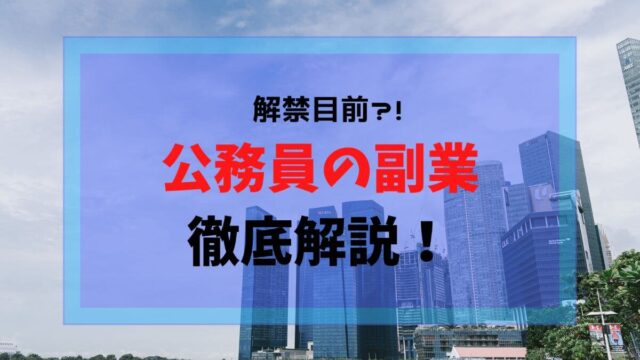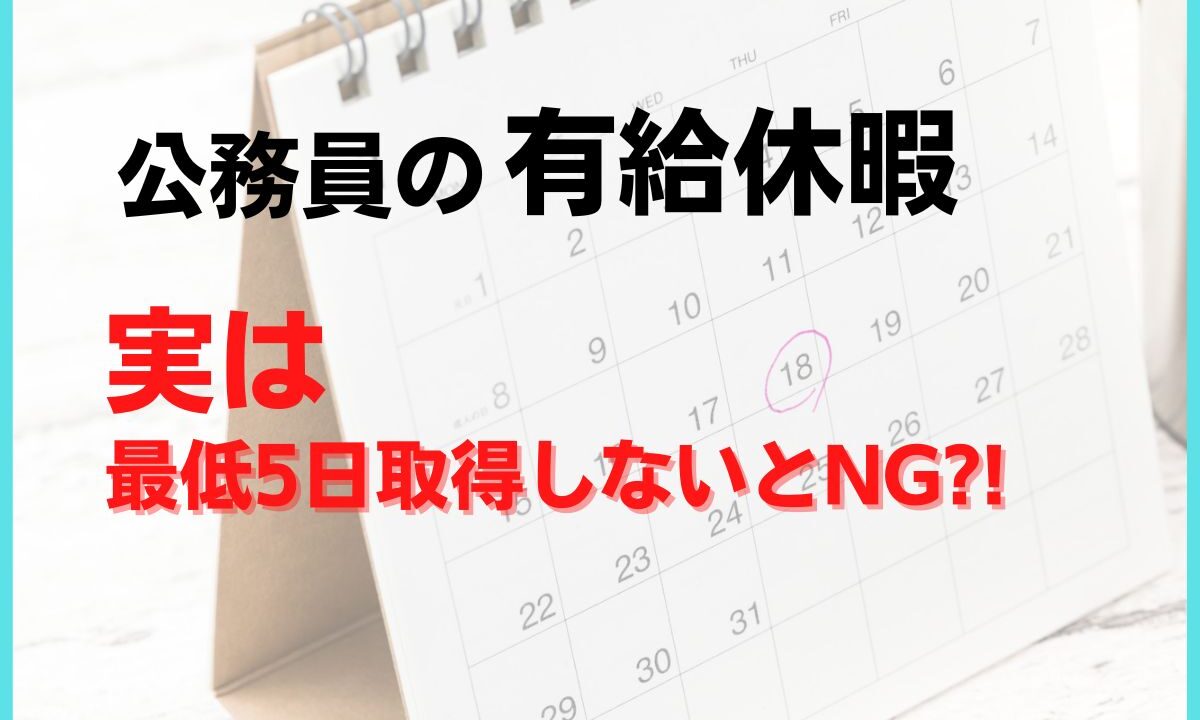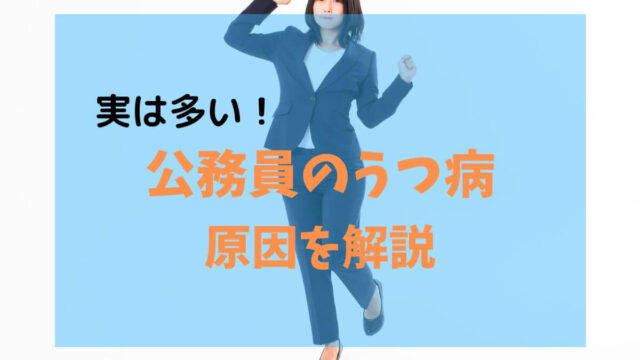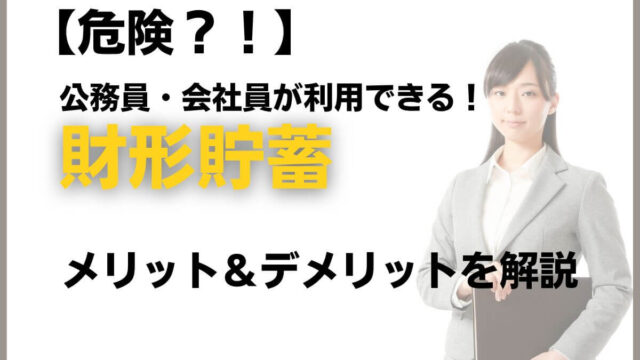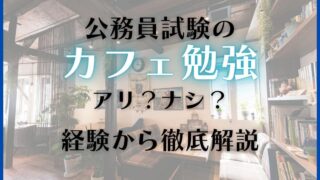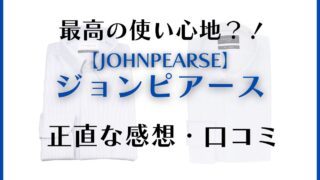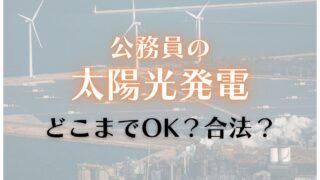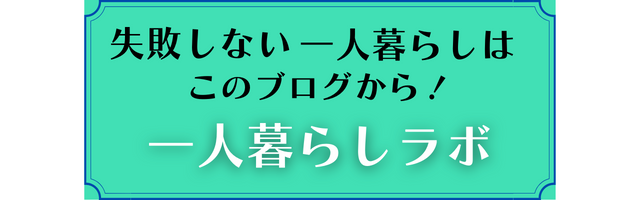「公務員って有給休暇を最低5日は取らなきゃいけないって本当?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に公務員1年目の方は遠慮してしまって中々有給休暇を使いにくいと感じている方も多いですよね。
筆者も特別区の職員として働く中で、有給休暇の制度について暗黙の了解となっている部分が多く、不安に感じることがありました。
そこで今回は公務員の有給休暇の取得義務や仕組みについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。
目次
国家・地方公務員は5日有給休暇を取らないといけない?
まずは公務員の有給休暇の取得義務について詳しくお伝えしますが、具体的に公務員の有給休暇の取得日数に決まりはあるのでしょうか。
結論からお伝えすると、国家・地方公務員の有給休暇はどんな役職であっても原則年5日取るようにルール決めされています。
国家公務員に関しては、人事院が平成30年8月10日に有給休暇の取得について、下記の具体的なルールを定めています。
さらに、民間労働法制における年次有給休暇の時季指定に係る措置を踏まえ、年次休暇の使用を促進するため、各省各庁の長は、休暇の計画表の活用等により、一の年の年次休暇の日数が10日以上の職員が当該年において年次休暇を5日以上確実に使用することができるよう配慮することとする。
平成30年8月10日 公務員人事管理に関する報告(30houkoku_jinjikanri.pdf)より一部引用
上記の内容をまとめると、1年に10日以上有給休暇の権利が付与される職員は最低でも年5日は有給休暇を消費しなさいという内容です。
地方公務員も国家公務員のルールに準ずる形で、年5日以上有給休暇を取得しなければいけないと決められていますよ。
公務員は有給休暇を取りやすい仕組みが整っている
公務員は有給休暇を最低5日消費しなければいけないということをお伝えしましたが、有給休暇の取得が義務付けられていても、自由な休みが取りにくいんじゃないのと不安に感じている人も多いですよね。
ただ、公務員は民間企業と比較すると、有給休暇を消費しやすい環境が整っています。
その理由についてはこちらの記事で詳しく解説していますが、民間企業と比較して福利厚生が整っていることや業務がマニュアル化されていることが大きな要因として挙げられます。
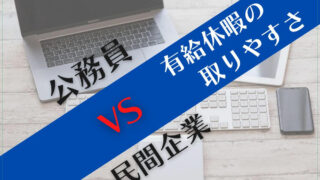
公務員が有給休暇を5日取得しなかった時の罰則は?
国家・地方公務員は比較的有給休暇を取りやすいとお伝えしましたが、中には業務が忙しくて年5日取り忘れてしまった場合にどうなるのか気になるという方もいますよね。
実際に人事課や財政課、企画課などの重要な部署では残業時間も多く、有給休暇を取れるタイミングが無いという可能性もありえます。
先程、公務員の有給休暇は5日取得が義務とお伝えしましたが、あくまで人事院からの通達であって、民間企業に対して適用される労働基準法と違い、法律で義務化されている訳ではありません。
そのため、仮に5日以上有給休暇を取得できなかった場合に、所属先や自治体が罰則を受けることはありません。
また、合計40日を上限に有給休暇は繰り越されますが、超えてしまった部分は権利が消滅してしまいます。
なるべく計画立てて取れるタイミングで速やかに消費出来ればベストですが、難しければ直属の上司や労働組合に必ず相談しましょう。
まとめ:公務員の有給休暇は5日消費が義務
今回は国家・地方公務員の有給休暇の取得義務について詳しく解説していきました。
民間企業と異なり、労働基準法は適用されないものの、国家公務員は人事院のルールで有給休暇を年5日以上取得することが決まっていて、地方公務員も準ずる形で年5日以上取得しなければいけないという訳です。
1年目だと有給休暇を使うタイミングも中々分からないという方が多いと思いますが、こちらの記事で解説している通り、公務員は1年目からでも有給休暇が取りやすいです。
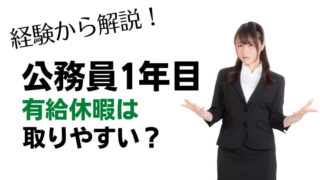
ぜひ今回の記事を参考に有給休暇制度を活用し、リフレッシュや自己研鑽に努めていきましょう。
以上ザワングでした。