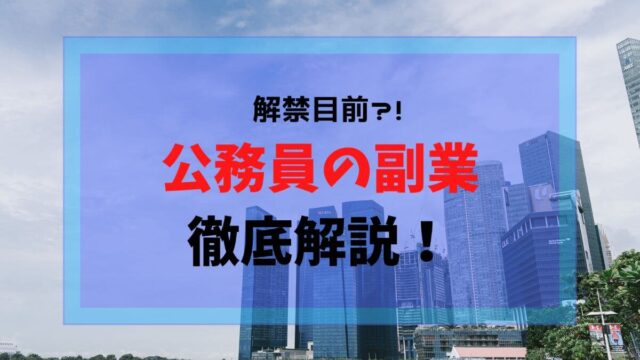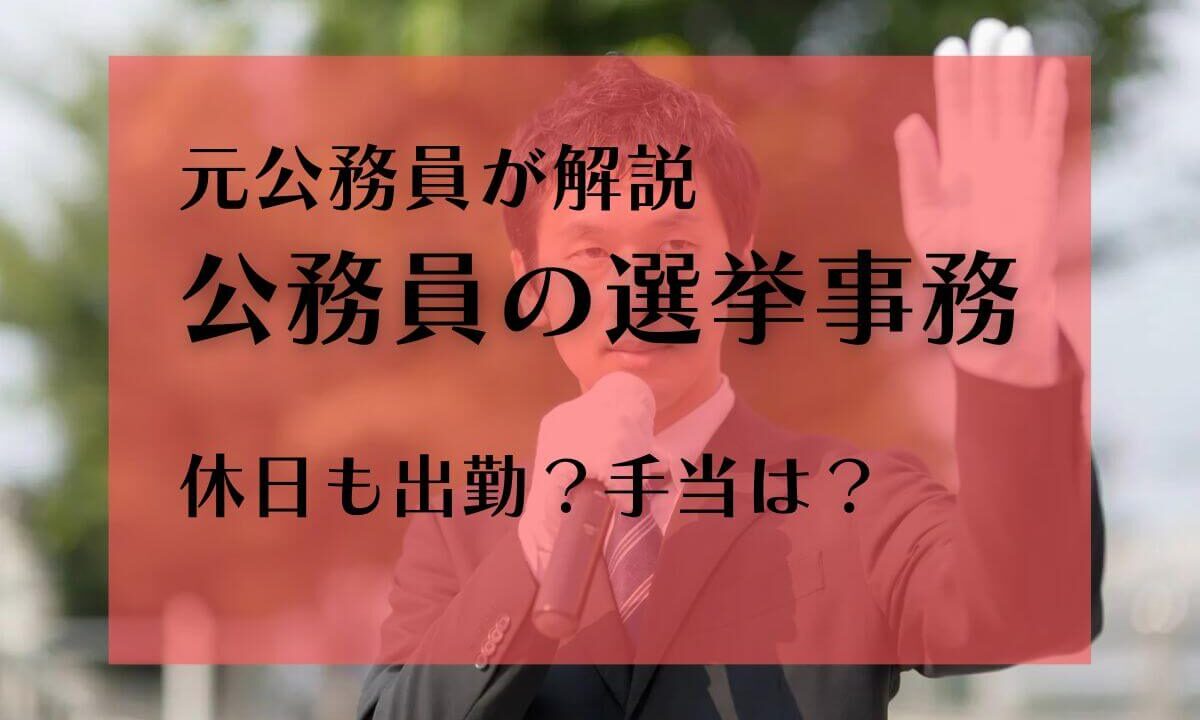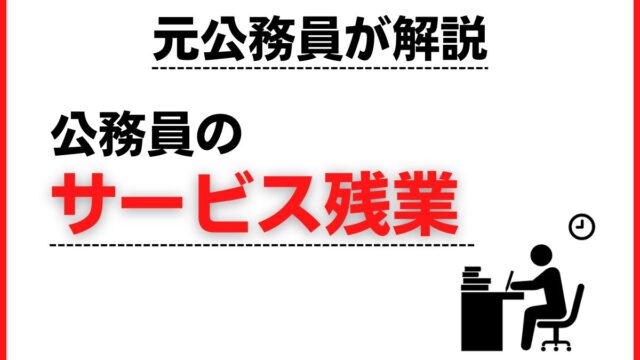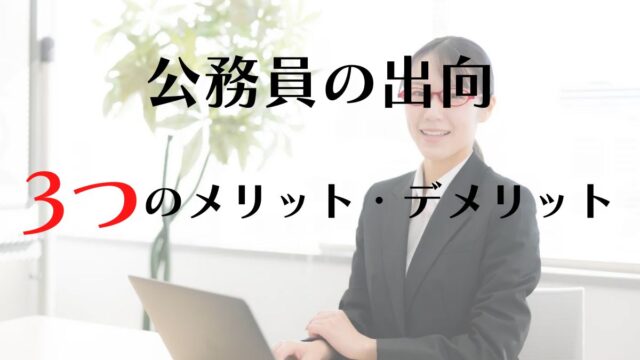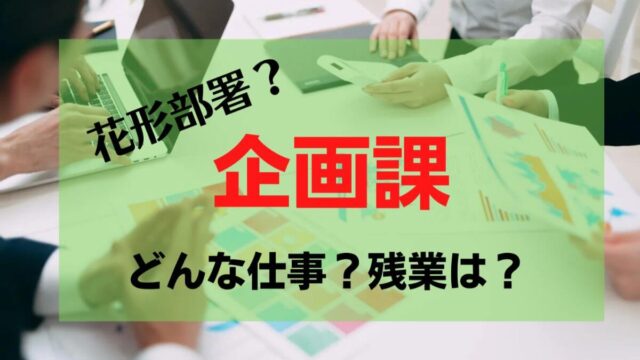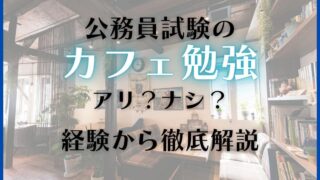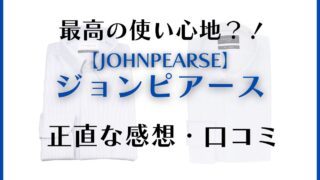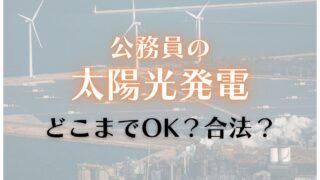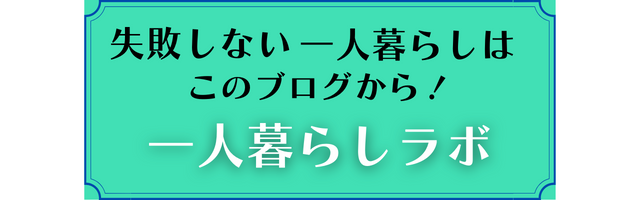市区町村の地方公務員は部署に関わらず、選挙の度に選挙事務の仕事があります。
ただ選挙事務と言っても具体的にどんな仕事をするのか、どれくらいの手当が貰えるのか、知っておかないと不安ですよね。
そこで今回は元公務員の経験をもとに市区町村の地方公務員が行う選挙事務の業務内容や報酬について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
市区町村地方公務員の選挙事務の業務内容は?
衆議院・参議院議員選挙や都道府県知事選挙、市区町村長選挙など、様々な選挙がある度に市区町村の公務員は、選挙管理委員会の応援業務という形で投票所の設営や準備、運営を行います。
選挙事務の業務を大きく分けると下記の3種類です。
・期日前投票
・投票日当日の投票
・開票事務
期日前投票の業務内容
期日前投票は公示の翌日から選挙投票日前日まで行われるもので、投票日当日の選挙事務同様、市区町村の職員が投票所の準備・運営を行います。
庁舎や出張所・ショッピングセンターなどの商業施設など様々な場所で行われるため、集合時間・解散時間もまちまちですよ。
また期日前投票の場合は、数日間に渡って行われるため、当日のような設営・解体準備をしなくても良い場合があります。
投票日当日の業務内容
投票日当日の投票事務は、庁舎や出張所、小・中学校の体育館などの投票所の設営から運営、片付けまでを通して行います。
とにかく準備することが多いので、当日の準備では間に合わず、前日に一度集合して1~2時間ほど設営準備をすることもあります。
選挙当日も朝6時頃に集合し、解散は夜8時半~9時過ぎになるため、合計で13時間以上も拘束されることになりますね。
開票事務の業務内容
開票事務は、投票が終わる夜8時過ぎに各投票所から投票箱が集められ、一枚一枚手作業で票を数える業務です。
選挙の種類や自治体によって、即日開票と翌日開票があり、業務内容は変わりませんが、行う時間帯が変わります。
即日開票の場合、勤務時間は開票が始まる夜8時前に集合し、長い場合は日付が変わる時間まで作業を行い、翌日開票の場合は、翌日の午前中に開票作業を行います。
選挙事務は地方公務員の小遣い稼ぎ?手当・報酬はどのくらい?

選挙事務でどんな仕事をするのかをお伝えしましたので、次は選挙事務の手当について見ていきましょう。
選挙事務に対する手当・報酬ですが、基本的には通常の時間外勤務手当と異なり、勤務時間に関わらず決まった金額が手当として支給されます。
ただし自治体によって手当支給のルールが異なる場合がありますので、注意が必要です。
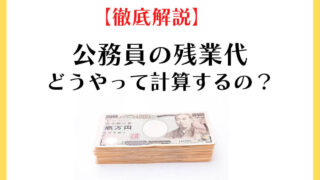
固定給のため、特に時給が安い20~30代の若手職員はかなりコスパが良く、自ら希望して選挙事務に従事する人も多かったです。
逆に言うと時給が高いベテラン職員でも若手と金額が変わらないため、年配の職員にとっては割に合わない仕事というイメージを持たれています。
期日前投票の手当・報酬は?
自治体によって異なりますが、平日と被る期日前投票の手当は時間外勤務分だけ支給されるか、固定給で5,000円~10,000円程度支給されます。
土休日の期日前投票は時間外勤務分の支給か、平日よりも割増された金額で支給される場合が多いですよ。
選挙当日の手当・報酬は?
選挙当日は自治体ごとに手当の額が決められていて、1万円~3万円ほどの手当が支給されます。前日に設営準備に参加した場合には追加で3000円~6000円程度割増でもらえる場合があります。
また、報酬とは別途に昼食のお弁当やお茶・お菓子代なども支給される場合がありますよ。
開票事務の手当・報酬は?
開票事務の手当も自治体によって異なりますが、5000円から1万円ほどの手当が支給されます。
開票が長引き深夜帯になる場合などは割増しで手当がもらえる場合もありますよ。
それぞれの選挙事務の手当額をまとめると下記の通りです。筆者の経験と友人等の話をもとにまとめていますので、自治体によって差異はあります。
| 期日前投票 | 時間外勤務分or5,000円~10,000円 |
| 投票日の選挙事務 | 10,000円~30,000円 |
| 開票事務 | 5,000円~10,000円(勤務時間によって追加で増額される場合も) |
選挙事務の手当はいつ貰えるの?手渡し?振込?
選挙事務の手当は時間外勤務手当と違い、金額が決まっているということをお伝えしましたが、この選挙事務の手当はいつもらえるのでしょうか。
自治体によって異なりますが、その場で手渡しされるわけではなく、翌月の給料日に他の給料とまとめて振り込まれます。
選挙の翌月の給料日には、選挙事務の手当が上乗せされていつもよりも数万円多く貰えるので、支給日がとても待ち遠しく感じますよ。
選挙事務の振り替え休日は貰える?実態は?
選挙事務の手当額について詳しくお伝えしましたが、ここまでお読みいただいた方の中には選挙に従事した分の振替休日を取得することはできるのか気になっているという方もいますよね。
結論からお伝えすると選挙事務に対しての振替休日はありません。
通常の休日出勤と異なり、休日出勤手当を貰う代わりに振替休日を取得することはできませんが、休日に従事した人は連勤となってしまうため、体を休める意味合いで選挙翌日に有給休暇を取得する人が多いです。
こちらの記事で詳しく解説していますが、公務員は比較的有給休暇が取得しやすいので、選挙事務の疲れをしっかりと取るためにも有給休暇を活用していきましょう。
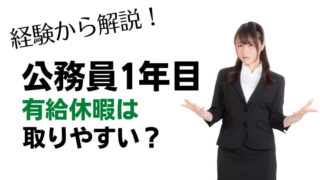
公務員の選挙従事の時の服装は?カジュアルでもOK?
これから選挙事務に従事をするという方の中には、どんな服装なら問題ないのか気になるという方も多いですよね。
期日前・当日の投票事務は市民の方と接することになりますので、派手過ぎず、ある程度清潔感のある服装でないといけません。ただ、かっちりとしたスーツを着ていく必要はなく、オフィスカジュアルな服装が最適です。
開票事務に関しては、市民の方と接することが無いため、私服で来る人もいます。悪目立ちしない格好であれば、ラフな服装でも問題ないですよ。
| 期日前・当日の投票 | 男女ともオフィスカジュアルな服装であればOK。 |
| 開票事務 | 服装の縛りなし。私服で来る人も多い。 |
まとめ:地方公務員の選挙事務を徹底解説
今回は市区町村の地方公務員が行う選挙事務の業務内容や手当額について詳しく解説しました。まとめると下記の通りです。
・選挙事務は「期日前投票」「投票日当日の投票」「開票事務」の3種類に分けられる
・時間外勤務手当と異なり、選挙事務は固定で手当額が決まっていることが多い
・休日の従事でも振り替え休日はないので、効率よく有給休暇を使おう
公務員の選挙事務は、特に若手においては時間外勤務手当よりもコスパよく手当が貰えるため、自ら進んで従事する人も多いです。
これから選挙事務に従事する方は、今回の記事を参考に業務内容や手当報酬額を確認してみましょう。
以上ザワングでした。